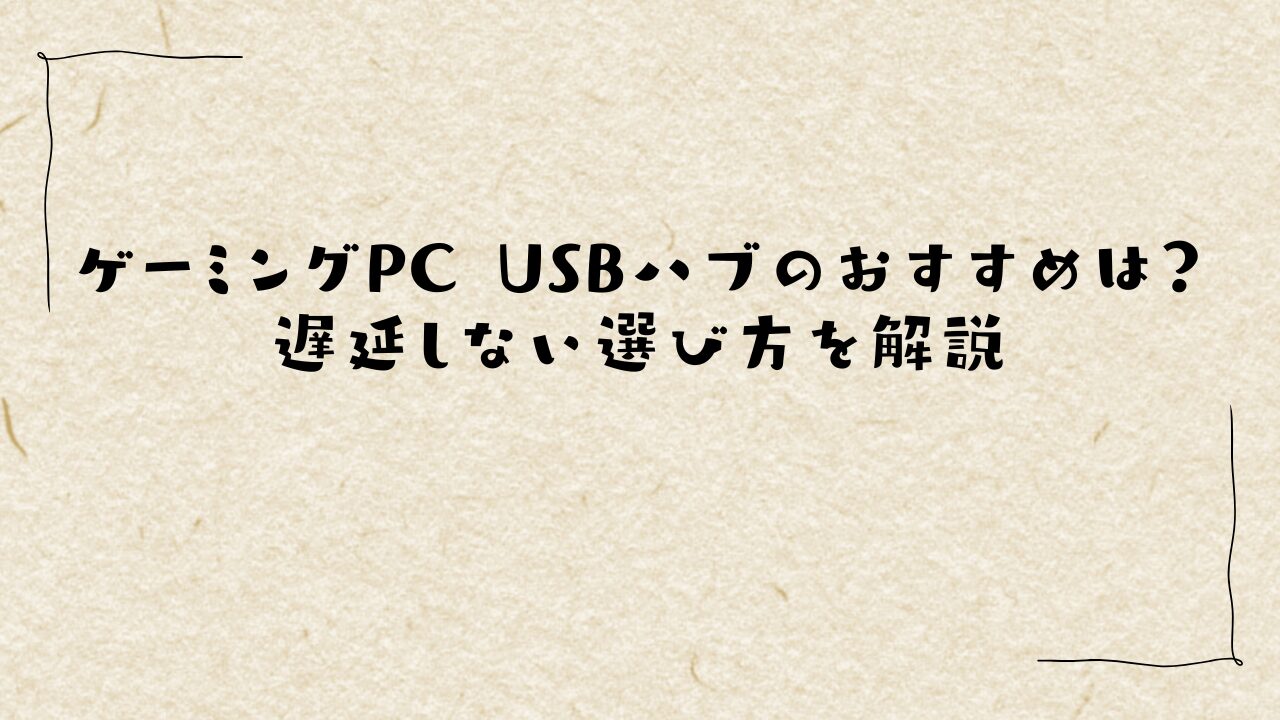ゲーミングPCで快適なプレイ環境を整えようとすると、マウス、キーボード、ヘッドセットなど多くのデバイスが必要になり、USBポートの増設を考え始めますよね。
しかし、USBハブがダメな理由は?といったネガティブな情報や、接続による遅延は発生しないのか、といった不安もつきものです。
そもそもゲーミングPCのUSBハブとは何ですか?という基本的な知識から、USBハブはセルフパワーとバスパワーのどちらがいいですか?という選択基準、ゲーミングpcと通常のusbとの違い、そしてポート数や挿す場所の考え方まで、気になる点は山積みです。
中には、PS5でUSBハブは使えますか?と家庭用ゲーム機での利用を考えている方もいるかもしれません。
この記事では、そんなあなたの疑問を解消し、最適なセルフパワー式のハブなど、後悔しないおすすめ製品の選び方を徹底的に解説します。
ポイント
- USBハブの基本と「遅延」や「電力不足」の真実がわかる
- ゲーミング用途に最適なUSBハブの選び方が理解できる
- セルフパワー方式とバスパワー方式の明確な違いがわかる
- 目的別におすすめの具体的なUSBハブ製品が見つかる
ゲーミングPC向けUSBハブの基本知識
- そもそもUSBハブとは?役割と必要性
- なぜ「USBハブはダメ」と言われる?主な理由を解説
- ゲーミングデバイスをUSBハブに接続すると遅延は起こる?
そもそもUSBハブとは?役割と必要性
USBハブは、一言で言えば「USBポートの分配器」です。パソコンに搭載されている1つのUSBポートに接続することで、複数のUSBポートを増設できます。ちょうど、部屋のコンセントが足りない時に電源タップ(延長コード)を使うのと同じようなイメージです。
特にゲーミングPCの環境では、以下のような多数の周辺機器(ゲーミングデバイス)を接続することが一般的です。
- ゲーミングマウス
- ゲーミングキーボード
- ヘッドセットまたはマイク
- Webカメラ(ゲーム実況などで使用)
- ゲームパッド(コントローラー)
- 液タブや外付けHDDなど
これだけのデバイスを接続しようとすると、PC本体のUSBポートだけではすぐに埋まってしまいます。そこでUSBハブを使いポートを増設することで、ケーブルの抜き差しをすることなく、すべてのデバイスを常時接続した快適な環境を構築できるのです。
ポイント
USBハブは、ポート数が不足しがちなゲーミングPC環境において、多数のデバイスをスマートに接続・管理するために必須とも言えるアイテムです。
なぜ「USBハブはダメ」と言われる?主な理由を解説
「USBハブは使わない方がいい」という意見を聞いたことがあるかもしれません。これには、主に2つの理由が関係しています。それは「電力不足」と「通信速度の低下」の可能性です。
電力不足による動作不安定
USBポートは、接続された機器に電力を供給する役割も担っています。USBハブ、特にACアダプターの無い「バスパワー方式」のハブは、PC本体の1つのUSBポートから供給される電力を、ハブに接続された全デバイスで分け合う形になります。
そのため、LEDで光るゲーミングマウスやキーボード、外付けHDDなど消費電力の大きいデバイスを複数接続すると、電力の総量が足りなくなり、デバイスが正常に認識されなかったり、動作が不安定になったりすることがあります。これが「USBハブはダメ」と言われる最大の理由です。
通信のボトルネック
理論上、1つのUSBポートの通信帯域をハブに接続した全デバイスで共有するため、速度が低下する可能性はあります。多数のデバイスが同時に大容量のデータ通信を行うと、渋滞のような状態になることが考えられます。
注意点
これらの問題は、USBハブの性能や種類を正しく理解し、用途に合った製品を選べば解決可能です。特に電力不足の問題は、後述する「セルフパワー方式」のハブを選ぶことで、ほぼ解消できます。
「USBハブはダメ」というのは、主に安価で電力供給能力の低いバスパワーハブを、消費電力の大きい機器で使ってしまった場合に起こるトラブルが原因で広まったイメージかもしれませんね。
ゲーミングデバイスをUSBハブに接続すると遅延は起こる?
結論から言うと、高品質なUSBハブを使用している限り、人間が体感できるほどの遅延(レイテンシー)は発生しません。FPSや格闘ゲームのような一瞬の反応が勝敗を分けるゲームにおいても、プレイに影響が出る心配はほとんどないと言えるでしょう。
一部の検証では、USBハブを介することで0.1ミリ秒(ms)以下のごくわずかな遅延が計測されることもあるようですが、これはプロゲーマーでも感知困難なレベルです。例えば、一般的な無線(ワイヤレス)マウスの遅延が数ms程度であることを考えると、USBハブによる遅延は無視できるほど小さいことがわかります。
むしろ、遅延を心配するよりも、前述した「電力不足」の方がゲームプレイに与える影響は深刻です。電力不足に陥ると、マウスのセンサーが飛んだり、キーボードの入力が途切れたりといった、明らかな不具合につながる可能性があります。
ポイント
ゲーミング用途でUSBハブを選ぶ際は、遅延を過度に心配するよりも、電力不足を起こさない安定したモデルを選ぶことが何よりも重要です。
ゲーミングPC向けUSBハブの選び方【5つの重要ポイント】
- 【最重要】給電方式で選ぶ|セルフパワーとバスパワーの違い
- ポート数と配置で選ぶ|接続したいデバイス数を想定
- USB規格と転送速度で選ぶ|USB3.0以上がおすすめ
- 接続端子の種類で選ぶ|Type-AとType-C
- あると便利な機能で選ぶ|個別スイッチや固定方法
【最重要】給電方式で選ぶ|セルフパワーとバスパワーの違い
USBハブの選び方で最も重要なのが「給電方式」です。これには「セルフパワー方式」と「バスパワー方式」の2種類があり、ゲーミングPCで使うなら、原則としてセルフパワー方式を強く推奨します。
| 給電方式 | 特徴 | メリット | デメリット | おすすめの用途 |
|---|---|---|---|---|
| セルフパワー | ACアダプターをコンセントに接続し、ハブ自体が独立した電源を持つ。 | ・電力供給が非常に安定している ・消費電力の大きい機器を複数接続しても問題ない | ・ACアダプターが必要で、配線が増える ・コンセント周りのスペースが必要 ・バスパワー型より高価な傾向 | ゲーミングデバイス、外付けHDD/SSD、プリンターなど |
| バスパワー | PCのUSBポートから電力供給を受ける。 | ・ACアダプターが不要で配線がスッキリ ・コンパクトで持ち運びに便利 ・比較的安価 | ・電力供給が不安定になりやすい ・消費電力の大きい機器には不向き | マウス、キーボード(LED無し)、USBメモリなど(ノートPCでの外出先利用) |
ゲーミングデバイスはLEDライティングなどで消費電力が大きいものが多いため、バスパワー方式では電力が足りず、動作が不安定になるリスクが高いです。安定したゲーミング環境を構築するためには、ACアダプター付きの「セルフパワー方式」を選びましょう。
迷ったらセルフパワー!これがゲーミングPC用USBハブ選びの鉄則です。後から「電力が足りなかった…」と後悔するのを避けるためにも、最初から安定したモデルを選ぶのが賢明ですよ。
ポート数と配置で選ぶ|接続したいデバイス数を想定
次に確認したいのがポートの数です。現在接続したいデバイスの数ピッタリではなく、将来的にデバイスが増える可能性を考えて、1〜2ポート多めのものを選ぶと良いでしょう。一般的には4ポートや7ポートのモデルが主流です。
また、ポートの配置も意外と重要です。幅の広いUSBメモリなどを接続する場合、ポート同士の間隔が狭いと隣のポートに干渉してしまい、使えなくなることがあります。
ポートの配置タイプ
- 上面配置:抜き差しがしやすく、機器同士が干渉しにくい。
- 側面配置:見た目がスッキリするが、機器によっては干渉の可能性も。
最近では、上面と側面にポートを分散して配置し、利便性を高めたモデルもあります。自分の使い方をイメージして、最適なポート数と配置の製品を選んでください。
USB規格と転送速度で選ぶ|USB3.0以上がおすすめ
USBには複数の規格があり、それぞれデータの転送速度が異なります。外付けSSDやUSBメモリなど、データの読み書き速度が重要になるデバイスを接続する場合は、高速な規格に対応したハブを選ぶことが重要です。
| 規格名(通称) | 最大転送速度 | 端子の色など | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) | 10Gbps | 青や赤色が多い | 高速な外付けSSD、動画編集など |
| USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) | 5Gbps | 青色が多い | 外付けHDD/SSD、Webカメラなど一般的な高速転送 |
| USB 2.0 | 480Mbps | 黒や白 | マウス、キーボード、ヘッドセットなど |
マウスやキーボードといった入力デバイスはUSB 2.0でも十分ですが、将来性を考えると、全てのポートがUSB 3.0(USB 3.2 Gen1)以上に対応したハブを選んでおくのが安心です。「このポートは遅いから…」といちいち考えずに済むため、ストレスなく使用できます。
補足:USB規格の名称について
USB規格の名称は統一が進み、現在では「USB 3.0」は「USB 3.2 Gen1」、「USB 3.1」は「USB 3.2 Gen2」と呼ばれるのが正式です。しかし、販売サイトなどでは古い名称が使われていることも多いため、両方の名前を覚えておくと混乱しにくいでしょう。
接続端子の種類で選ぶ|Type-AとType-C
USBハブをPCに接続するためのケーブルの端子形状も確認が必要です。主に「Type-A」と「Type-C」の2種類があります。
- USB Type-A:最も一般的な長方形のUSB端子です。ほとんどのデスクトップPCや多くのノートPCに搭載されています。
- USB Type-C:比較的新しい上下対照の楕円形の端子です。MacBookや薄型ノートPC、最近のPCケースのフロントポートなどに採用されています。
自分のPCにどちらのポートが空いているか、あるいはどちらに接続したいかを確認し、それに合った接続端子のUSBハブを選びましょう。ハブ側(増設される側)のポートはType-Aが主流ですが、最近ではType-Cポートを増設できるモデルも増えています。
あると便利な機能で選ぶ|個別スイッチや固定方法
基本的な性能に加えて、使い勝手を向上させる便利な機能が付いているかもチェックしましょう。
個別スイッチ
ポートごとに電源のオン・オフを切り替えられるスイッチが付いているモデルです。使用しないデバイスへの給電をカットして節電したり、接続はしたままで認識だけをオフにしたい場合に便利です。ケーブルを抜き差しする手間が省けます。
マグネットやクランプによる固定
本体の裏面にマグネットが内蔵されており、スチール製のデスクの脚やPCケースの側面などに貼り付けて固定できるモデルがあります。また、デスクの天板を挟んで固定するクランプ式のモデルも存在します。これらの機能があると、デスク上がスッキリし、ケーブルの重みでハブが動いてしまうのを防げます。
まとめ:選び方の優先順位
- 給電方式:セルフパワー方式を最優先
- ポート数:必要数+αの余裕を持つ
- USB規格:USB 3.0以上を基準に選ぶ
- その他:接続端子や便利機能を確認する
【2025年版】ゲーミングPC向けUSBハブおすすめ6選
- 【セルフパワー】安定性重視!消費電力の大きい機器向けおすすめ3選
- 【バスパワー】手軽さ重視!持ち運びにも便利なモデルおすすめ3選
ここでは、これまでの選び方を踏まえ、ゲーミングPC環境に最適なUSBハブを「セルフパワー」と「バスパワー」に分けてご紹介します。
【セルフパワー】安定性重視!消費電力の大きい機器向けおすすめ3選
デスクトップPCでどっしりと腰を据えてゲームをするなら、電力不足の心配が一切ないセルフパワー方式が最適解です。
1. エレコム U3H-T719SBK
セルフパワーハブの決定版とも言える人気モデルです。USB3.0ポートを7つ搭載し、多くのゲーミングデバイスを接続しても安定した電力供給を実現します。強力なマグネットが背面に付いているため、スチールデスクの側面やPCケースにピタッと固定できるのが非常に便利。ケーブル長も1.0mと余裕があり、取り回しやすいのも魅力です。
2. Anker 7-Port USB 3.0 Hub
モバイルバッテリーで絶大な信頼を誇るAnker製のセルフパワーハブです。7つのUSB3.0ポートに加え、スマホやタブレットの急速充電に特化した充電専用ポートも備えています。データ転送と充電を両立したい方におすすめ。Ankerならではの高品質と手厚いサポートも安心材料です。
3. サンワサプライ USB-3H703BKN
このモデルも7ポートのUSB3.0ハブですが、特筆すべきは急速充電対応ポートを3つも搭載している点です。コントローラーやヘッドセット、スマートフォンなど、充電が必要なデバイスを複数持っているゲーマーには非常に重宝します。安定したデータ転送と強力な充電能力を兼ね備えた、頼れる一台です。
【バスパワー】手軽さ重視!持ち運びにも便利なモデルおすすめ3選
消費電力の少ないデバイスが中心の場合や、ノートPCで外出先に持ち出す用途であれば、コンパクトなバスパワー方式も選択肢に入ります。
1. Anker USB3.0 ウルトラスリム 4ポートハブ
バスパワーハブのベストセラーモデルです。厚さ約1cmという驚異的な薄さとコンパクトさで、持ち運びに全く邪魔になりません。4つのポートは全てUSB3.0に対応しており、外出先でマウスやUSBメモリを接続する際に十分な性能を発揮します。価格が手頃なのも嬉しいポイントです。
2. バッファロー BSH4U300U3
このモデルはバスパワーでありながら、背面にマグネットが付いているユニークな製品です。自宅のデスク周りで使う際に、ちょっとした金属部分に固定しておけるため、配線がスッキリします。コンパクトさと設置のしやすさを両立したい方におすすめです。
3. エレコム U3H-S418BBK
ポートごとに個別スイッチが付いたバスパワーハブです。マグネットも搭載しており、使い勝手はセルフパワーの上位モデルに引けを取りません。消費電力の少ないデバイスを複数接続し、使用状況に応じてオン・オフをこまめに切り替えたい場合に非常に便利です。
USBハブに関するよくある質問
- PS5やSwitchなどの家庭用ゲーム機でも使えますか?
- USBハブは何個まで連結(タコ足配線)できますか?
- USBハブを使わずにポートを増やす方法はありますか?
PS5やSwitchなどの家庭用ゲーム機でも使えますか?
はい、多くのUSBハブはPS5やNintendo Switchでも使用可能です。
例えば、PS5ではコントローラーの充電や有線キーボードの接続、Switchでは有線LANアダプターや複数コントローラーの接続などに活用できます。ただし、全てのハブが対応を保証しているわけではないため、商品説明に「PS5対応」「Switch対応」といった記載がある製品を選ぶとより確実です。
特に、消費電力がシビアな家庭用ゲーム機で使う場合も、安定動作のためにセルフパワー方式のハブを選ぶことをおすすめします。
USBハブは何個まで連結(タコ足配線)できますか?
USBの規格上は、ホストコンピューターとデバイスの間に最大5段階までハブを連結できます。また、1つのホストコントローラーに接続できるデバイスの総数は最大127個とされています。
しかし、これはあくまで理論値です。ハブを連結すればするほど電力供給は不安定になり、通信の遅延やエラーのリスクも増大します。トラブルを避けるためにも、USBハブのタコ足配線は避け、PC本体のポートから直接接続するか、ポート数の多い1台のハブにまとめるのが賢明です。
非推奨
USBハブの多段連結は、動作の不安定を招く大きな原因となります。できる限り1台のハブで完結させるようにしましょう。
USBハブを使わずにポートを増やす方法はありますか?
はい、あります。デスクトップPCの場合、「USB増設インターフェースカード(PCI Expressカード)」をマザーボードの空きスロットに増設する方法があります。
この方法は、PCの内部に直接ポートを増設するため、USBハブのように外部の配線が増えることがなく、非常に安定した電力供給と通信が可能です。PCのケースを開けてパーツを増設する作業が必要になるため、ある程度のPC知識が求められますが、最もスマートで確実な増設方法と言えます。
自作PCユーザーやPCのカスタマイズに慣れている方であれば、PCIeカードでの増設が最もおすすめです。見た目もスッキリし、パフォーマンスも最大限に引き出せますよ。
まとめ:最適なUSBハブで快適なゲーミング環境を構築しよう
最後に、この記事の要点をリストで振り返ります。
- ゲーミングPCでは多くのデバイスを接続するためUSBポートが不足しがち
- USBハブはポートを手軽に増設できる便利なアイテム
- 高品質なハブを使えばゲームプレイに影響する遅延はほぼ発生しない
- 「USBハブがダメ」と言われる主な原因は電力不足による動作不安定
- この電力不足はACアダプター付きのセルフパワー方式ハブで解決できる
- ゲーミング用途ではセルフパワー方式のUSBハブが最もおすすめ
- バスパワー方式はコンパクトだが消費電力の大きい機器には不向き
- ポート数は将来を見越して必要数より1~2個多いものを選ぶと安心
- データ転送速度が重要な機器を繋ぐならUSB3.0以上の規格を選ぶ
- マウスやキーボードならUSB2.0でも問題なく動作する
- 自分のPCのポート形状に合った接続端子(Type-A/Type-C)のハブを選ぶ
- 個別スイッチやマグネット固定機能があると利便性が向上する
- PS5やSwitchなどの家庭用ゲーム機でもUSBハブは利用可能
- ハブの多段連結(タコ足配線)はトラブルの原因になるため避けるべき
- より安定性を求めるならPC内部に増設するPCIeカードも選択肢になる